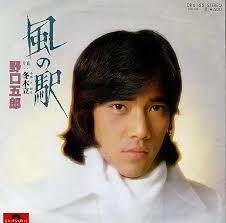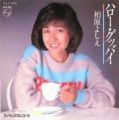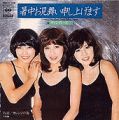今回の1曲セレクトは、「ロンリー・ウルフ」沢田研二です。
まずはデータです。
・タイトル ロンリー・ウルフ
・アーティスト 沢田研二
・作詞 喜多条忠
・作曲 大野克夫
・編曲 後藤次利
・リリース日 1979年9月21日
・発売元 ポリドール
・オリコン最高位 18位
・売り上げ枚数 8.9万枚
もうね、いつものマクラ言葉になってますが、「久しぶり」の1曲セレクトです。
毎度毎度、間が空いてしまってあいスミマセンと頭を下げたくなってしまいます。
相変わらずリアル仕事が忙しくて、なかなか筆が上がらない状態が続いてまして。。。
暫くは長ーい目で見ていただけるとありがたいです。
さて、長い間仕事をしてくると何もかもが上手く行く事もあれば、逆に全く上手く行かない事もありますわな。
ヒット曲も同じで、どんな大物アーティストでも、いつもいつも大ヒットするわけぢゃない。
まあ、最近は楽曲内容にかかわらず、どの曲もミリオンセラーを続けている某アーティスト見たいな方たちもいるみたいですが。。。
こと、昔、楽曲志向が高かったころは、超一線級のアーティストでも楽曲によっては、コケてしまうこともあったわけです。
今回はそんな1曲を
沢田研二「ロンリー・ウルフ」
いやいや久っさびさのジュリーですな。1曲セレクトで書くのいつ以来だろう?
この曲、覚えている方どのくらいいるでしょうねぇ。
なんせ、人気全盛の頃、突然ベストテン入りを外した曲なんでね。
しかも、臨発ならいざしらず、ローテーションの定期リリースでしたからねぇ。
時期的には、今から41年前、1979年の今頃の曲だったんですけどね。
曲順から言うと、「OH!ギャル」と「TOKIO」の間のシングルですね。
さすがにジュリー第3期のオープニンングと言うべき「TOKIO」を知らないという方は少ないでしょうけど、もしかすると「OH!ギャル」は知らない方もいるかなぁ。
まあ、死角っちゃ死角なのかもしれないけど、ジュリーが化粧した、ゲイぢゃねーのかと言われた曲で、ベストテン入りも果たし、売り上げ的にも27万枚ほど売れてましたんでね。
・・ということで、ヒット曲とヒット曲に挟まれた本当に「谷間」のシングルなんだよね、この「ロンリー・ウルフ」っていうのは。
突然ベストテン入りも果たせず、売り上げも10万枚にも届かず。。という塩梅でしたから。
・・・・なんて、さぞかし当時から知ってましたよ〜・・・風に書いてるワタシも、正直、「ザ・ベストテン」しか情報がなかった、ヒット当時は知らなかったんだけどね。。




いや、もしかするとラジオかなんかで聴いていたかもしれない。でも、記憶に残るほど聴き込んでなかったのは事実ですね。
意識して聴いたのは、83年に買った「沢田研二大全集」みたいなカセットに収録されていたのを聴いてからなんだよね。
もちろん、そのころは、「あ〜あの売れなかった曲」くらいの認識はあったんだけど。
でも、売れなかったから「駄曲」だったのか・・と言えば、さにあらず。
それまでのアウトローなジュリーを彷彿とさせるような佳曲だ。
むしろ、軽いタッチのポップスだった前曲の「OH!ギャル」よりも、ジュリーらしい曲だなと感じたな。
静寂感のある少し重め曲調は、秋というリリース時期にもマッチしていたし、そういう意味では前年の「LOVE(抱きしめたい)」に近い曲調ではある。
シングルとして「尖って」いないのかというと、これまたそうではなく、それなりの尖りがあり、シングルタイプの曲でもある。
ぢや、なんで、売れなかったのか?
同じ暗めの重いバラードではあるものの前年の「LOVE(抱きしめたい)」のような華がない。
本当に「重いだけ」のバラードなんだよ。
ジャケットのそれと同じでどこまでもモノクロのイメージ。確かにアウトローなジュリーを演出するにはこのイメージでも間違いではないのかもしれないけど、今一つ引っかかりないのは事実なんだよね。
加えて、致命的だったのは「時代の流れ」だろうなぁ。
1年前の78年までの時点では、アウトローというシチュエーションでも充分行けたんだろう。ただ、78年⇒79年の間に時代は大分動いていたんだよね。
勿論78年時点でもその流れは始まっていたけど、ヒットの主役は歌謡曲からニューミュージックへという変化。 それと79年は「JAPAN AS NO.1」と呼ばれた年。7月にSONY WALKMANが発売され、音楽も含め、世の中の意識もこの1年の間に大分変化してたんだよね。
つまりさ、アウトローっていうシチュエーションも78年は「カッコよかった」んだけども、79年ではアナクロだったわけですわ。
だからなのか、この頃のヒット曲と一緒に続けざまにこの曲を聴いてみると、この曲は明らかに浮いた感じがするんだよなぁ。
浮かんでくる絵面は79年の・・というよりも75年の・・・って感じがしてさ。
うん、この曲1曲単体で聴く分には充分かっこいいんですよ。 でも何曲かまとめて聴くとやっぱり時代錯誤的な感覚なんだよなぁ。
手元に月刊・明星付録の歌本「YOUNG SONG」1982年7月号がある。この号での連載企画「82年MUSIC PEOPLEインタビュー」にジュリーのインタビュー記事が掲載されているんだけど、そのなかに
「「TOKIO」は出すのが半年遅かった。その前に「ロンリー・ウルフ」をだして失敗するんですよ。それまでにある程度、売れるという事を経験したから、じゃあ、今度はスローな曲を歌って沢田も歌がうまいと思われたくて出したのが失敗」
と、ジュリー自ら、時代の変化に気が付き、この曲のリリースは失敗だったことを認めてたりする。
スローな曲を歌って、歌がうまいと認められたい・・というのことも、まあ、確かにわからなくもないですけどね。



ただ、じゃ、このインタビューのように「TOKIO」をもう半年早く出して、それでよかったのか・・というのも、個人的にはちょっと疑問ではあるな。
あれは、1980年1月1日リリースっていう、「軽薄短小」な80年代という時代のオープニングを飾ったからこそ、より価値が上がったような気もするし。。
79年後半とはいえ、70年代に「TOKIO」ではちょっと、時期が早かったんじゃないかと、今となっては思えたりね。
・・・ということは、あくまで「つなぎ」という意味も込めて、この「ロンリー・ウルフ」って曲のリリースも、もしかすると必然だったのかもしれないな。
うーん、確かに「モノクロ」のイメージではあるけど、今VTRを見ると男の色気が凄いね。いまは、こんな、ただ佇むだけで存在感のあるアーティストって少ないからなぁ。
バックは井上堯之バンドですね。 確かバックバンドはこの曲までで、この後「オールウェイズ」に変わったんじゃなかったっけな。
↑のように、この曲のイメージはアナクロだって感じたのは、多分に井上堯之のサウンドも関係しているんだろうね。
少し埃にまみれたような骨太でアウトローなサウンドは、紛れもなくかっこいいし、誰が何と言おうとも個人的にはジュリーには、このサウンドが一番しっくり来るんだけども。
如何せん、70年代という時代を彷彿させる音なんだよね。時代の流れには勝てなかった。
この曲をもって、ジュリーのバックバンドから引退⇒解散となるわけだけど、これはしょうがなかったんじゃないのかなぁ。
よろしかったら、ポチッと押してね
にほんブログ村