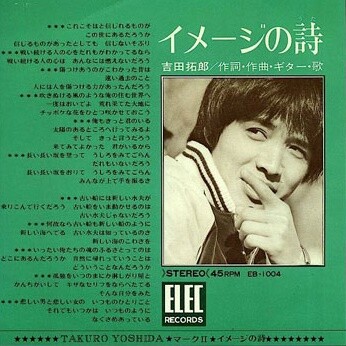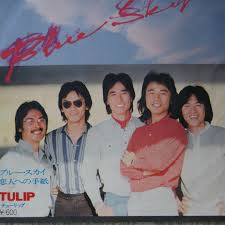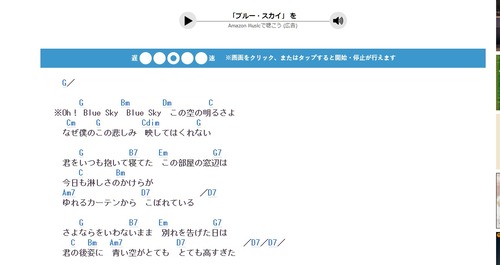今回の1曲セレクトは、「君に会いたい」ザ・ジャガーズです。
まずはデータなのだ。
・タイトル 君に会いたい
・アーティスト ザ・ジャガーズ
・作詞 清川正一
・作曲 清川正一
・リリース日 1967年6月1日
・発売元 フィリップス
・オリコン最高位 - 位
・売上げ枚数 - 万枚
今回はマクラなしで、のっけから本題。
久々にG.Sなど持ってきましょうか。
ジャガーズの「君に会いたい」
この曲、ずっと持ってこようと考えていたんだけども、今一つきっかけを思いつかなかったんで、ずっとストックしてた曲なんだけども、前回の、吉田拓郎氏の「イメージの詩」を書くにあたって、いろいろネットみてたら、なぜか、この曲にあたったんだよね。
この曲がリリースされたのは1967年6月。 まだ、オリコンは始まっていないんで、実際のヒット時期というのが分からないんだけども、あの頃は少なくとも「初動のみ」のヒットということは、ないだろうからさ。
・・ということは、1967年夏にかけてヒットしていただろうという「推定」で引っ張ってきたんだけどね。
もっとも、黒沢進氏著「日本の60年代ロックのすべて」によると、
爆発的なヒットではなかったが、67年夏から秋にかけてヒットした
・・とあるので、もしかすると、実際のヒット時期は、もう少し後だったかもしれないけど。。。
うん、1967年(昭和42年)といえば、ワタシゃ、−2才。 まだ生まれておりません。。。
なので、リアルタイムでは聴いてないし、実際にヒットしていた時期も体験していないので、、資料がない限りは推定で考えなきゃいけないんだけども。。。。
・・・ということで、この曲がヒット当時してた頃は、まだ生まれていなかったわたしが、初めてこの曲を知ったのは、実は1981年だったりするんだよね。
なぜ?
覚えてないですかねぇ、1981年夏、アサヒミニ樽のCMでこの曲が使われていたのを
↓ コレ
そういえば、真行寺君枝さんっていましたねぇ。いまはどうなさっているんだろう?
それよりも、風間杜夫、平田満の「蒲田行進曲」コンビでこのCMに出てたのは、知らなかったわ。
ちなみに映画「蒲田行進曲」が公開され、一大ブームを巻き起こすのは、この次の1982年になる。
まあ、いずれにしろ、なんか知らないけど、81年当時、このCMら引っかかっちゃったんだよな。
CMだけでなく、BGMの「君に会いたい」にも引っかかった。
なんで、当時、この曲に引っかかっただろうねぇ・・とも思ったりしたんだけども、考えてみれば、時代はG.S回帰だったんだよね。 1981年って。
G.Sの一大ブームを作った、いわいる「A級」のG.Sグループが相次いで解散、ブームの終焉を迎えたのが1971年。
それから丁度10年・・ということで、G.S回帰の動きを見せたのが1981年だったわけなんだよね。
ワイルドワンズが、夏限定で再結成したのが1981年だったし。 そもそも、ジュリーが「G.S I LOVE YOU」というアルバムをリリースし、これを契機にタイガース再結成に向けて動き出したのも1981年だったし。
ま、初めは1981年の1月に、数々のG.Sグループが出演した、「ウエスタンカーニバル」の舞台となった有楽町の「日劇」(日本劇場)が閉館したのが1981年1月。と同時に「さよならウエスタンカーニバル」という特別公演が1981年1月にあり、それを受けて、夏にかけて一時的ではあるけど、G.Sが盛り上がったわけなんだよね。
実際のヒット曲の傾向としても、ジュリーの「おまえがパラダイス」をはじめとした、50's〜60'sのオールディーズっぽい曲とか、それこそG.Sの頃のガレージっぽい曲とか、今考えると、結構多いんだよね、1981年って。
それを考えるとさ、この年1981年の「顔」である、「ルビーの指環」をはじめとした一連の寺尾聰ブームっていうのも、あながち偶然ではなかったような気がするんだよね。
うん、寺尾氏も、もともとは「サベージ」っていうG.Sのベーシストだったわけだしさ。G.Sとは切っても切れない訳じゃん。
そんな傾向にあったからさ、G.Sをリアルタイムには経験していなかったワタシは、このテのガレージっぽい音が、逆に新鮮、 先端の曲のように思えたんだよね。
だから、↑のサントリービア樽のCMで使われていたこの「君に会いたい」って曲が、まさか、
あの時点で10数年前の曲とは知らなかったからさ。新曲だと思ってたの。
いつリリースされるんだろうな。。。とか。。。




まあ、その前に、あの当時曲名すら知らなかったんだけども。




今、昭和歌謡が若いコたちの間で流行っているけど、、恐らくは、1981年頃、ガレージっぽいG.Sの曲を聴いて新鮮に思えるのと、同じような感覚なんだろうな。
まあ、1981年の時のG.S熱は、実際に「タイガース」が再結成したことで一旦終焉したんだけども、その後1986〜1987年にかけて、ネオG.Sという形で、再度、ガレージブームが来たじゃん。
あのとき、ワタシも本格的にG.Sに嵌って、CD集めてたら、この曲が収録されててさ。
そのとき、「あの曲だ」と思うとともに、初めて、曲名、アーティスト名、いつのリリースだとか、もろもろ知ったわけなんだけどもね。
いまでも、G.Sのガレージっぽい音って好きなんだよなぁ。
なんでなのか、よくわかんないけど、血が騒わぐというかさぁ。
考えてみれば、死んだオヤジが、「ベンチャーズ」か好きでさあ、車のカーステでよく聴いてたからなぁ。 その影響なのかしらん!?
なにより無国籍な音楽っぽいところがいい。 洋楽と言えば洋楽だし、 歌謡曲と言えば歌謡曲だし、ロックといえばロックだし。。。
どう解釈しても、あながち間違いではないというがいい。 節操がないんだよね。
それが、実に日本っぽいじゃん。
このジャガーズの「君に会いたい」って曲にしても、ぱっと聴きは、歌謡曲っぽいけど、100%歌謡曲とも言えない。かといってロックでもない。
バックのギターのリフはアラビア風だったり、口笛の旋律が怪しげだったり、一見よくわかんない世界なんだよね。それでいてメロディが刺さってきたりしてさ。
そんな一見バラバラな世界観が混ざり合うと、あーら、不思議。 いいじゃないの? って曲になる。
これこそがG.Sの真骨頂だったりするんだろうな。
ジャガーズとしては、デビュー曲のこの曲は違うけど、3枚目シングル「マドモアゼル・ブルース」からは主に筒美京平氏が作曲を担当するようになる。
それによって、ややガレージ感が薄れてきたように感じるのは、私だけでしょうかねぇ。。。。
よろしかったら、ポチッと押してね
にほんブログ村